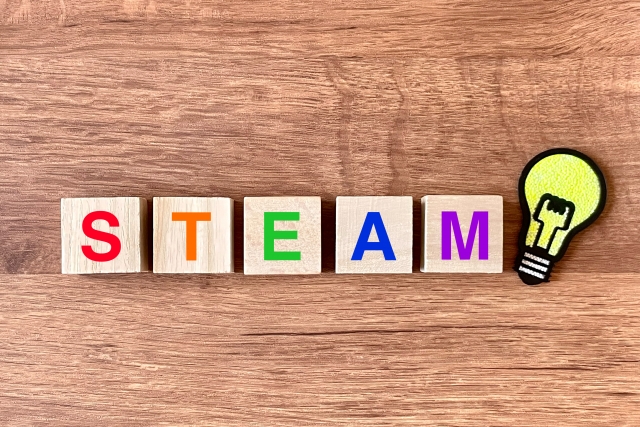STEAM教育とは
Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Arts(芸術)、Mathematics(数学)の5つの分野を統合した教育です。STEAM教育では、これらの分野を横断的に学習することで、問題解決力や創造力を育てます。
S
STEAM教育の科学は、子どもがさまざまな物事に好奇心を持つための役割を持っています。科学の範囲は、植物や動物、人体、元素など、身近な世界をつくり出している原理から宇宙など全てです。研究活動を通じて未来の研究者を育成します。
STEAM教育を通じて、数理的思考の土台となる、課題や法則に気が付く力を養います。先生は子どもに対し、実験やフィールドワークを通じて数理的思考の苦手意識を取り除くことが求められます。
さらに文部科学省では、先進的な理数系教育を実施している高等学校等を「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」に指定し支援する取り組みを実施しています。2002年から始まり、毎年20校以上が選ばれています。
T
STEAM教育の技術では、プログラミング学習等によって「論理的思考力や課題解決力」を養います。2020年より、小中学校でのプログラミング授業が必修となりました。
プログラミング的思考を育成することはITに負けない発想力を伸ばすだけでなく、将来のキャリアの選択肢を増やしたり、エンジニア不足を解消したりといった副次的な効果も見込まれています。
プログラミングは地道で細やかな作業が必要となるため、子どもが苦手意識を持ちやすい科目です。先生は子どもの成長過程に合わせて楽しいと感じるアプローチが必要です。
海外の教育機関はマインクラフトでのプログラミング学習など、ゲーム感覚でプログラムに触れていく授業が進んでいます。他にも音楽とプログラミングを組み合わせて作曲したり、ロボットにプログラミングを予測させたり、プログラミングに触れる機会は増えてきています。
E
STEAM教育の工学では、産業で必要となる「生産力」や「空間的把握能力」の育成に役立ちます。
STEAM教育で実践されている授業としては、自分たちで作成したプログラミングで自走するロボットを工作したり、図面を引いて限られた素材で製品を作成したりなど、かなり実践的な教育が行われています。
現在では小学校でも導入できる安全なロボットキットが多く開発されています。
A
STEAM教育の芸術では、自由な発想力や想像力を育み、作品を生み出すことで「創造力」を育てます。また芸術では自分のイメージや考えを言語化し、表現する・伝える力が必要となります。その過程で社会の一員として生きていくために必要となる力を鍛えることもできるのです。
STEAM教育が対象とする芸術の範囲は、科目としての美術の範囲よりも大きなものとなります。ダンス・演劇・音楽といった舞台芸術、写真・絵画・デザインと行った視覚的芸術、3Dプリンタやグラフィックアート等と、芸術性および創造性を育む幅広い分野が含まれています。
またSTEAM教育のAには、「教養」の意味を持つ「リベラルアーツ(Liberal Arts)」も含まれています。そのため人文科学、社会科学、自然科学、学際・統合科学といった幅広い分野の学びも求められています。
先生はSTEAM教育のAを美術や総合といった科目で絞り込むのではなく、幅広く知識に触れ、興味を引き出す授業の仕組みをつくりましょう。テーマ研究の発表会やブレインストーミングなどの機会を多く持たせることで、表現力を鍛えることができます。
M
STEAM教育の数学では公式などの法則に触れ、「論理的思考力」を養います。
数理的な考え方を学ぶことで、STEAM教育での様々な科目に役立てることができるのです。
STEAM教育は4つの数理的教育で課題を解決させる力を伸ばし、芸術科目で自由に創造、表現する力を伸ばします。
最近ではSTEAMSという単語を見ることがありますが、こちらはSTEAMにSports(スポーツ、運動)を追加した単語になります。ひらめきや考える力だけでなく、それを実現するための協調性や体力を付けようということを目標にした教育方針です。
そもそもSTEAM教育という考え方はどのように始まったのでしょうか?
STEAM教育に目が向けられるようになった背景と、実際の取り組みを見ていきましょう。